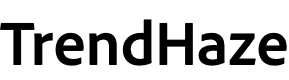タモリステーションが迫る!南海トラフ地震の脅威と防災対策
タモリが高知県で南海トラフ地震の現地調査を敢行
日本の人気タレント、タモリが司会を務めるテレビ朝日の特別番組「タモリステーション」が、3月7日に放送されました。今回のテーマは、今後30年以内の発生確率が約80%とされる南海トラフ地震です。この地震は、東日本大震災の約17倍の規模で、最悪の場合32万人の死者が出ると想定されている巨大地震。私たちがどのようにこの脅威に立ち向かうべきかを専門家と共に探りました。
“日本一危険な町”黒潮町の防災対策
タモリさんは、高知県の黒潮町を訪れました。ここは、最大津波高34.4メートルと、日本で最も高い津波が想定されている場所。町には6基の津波避難タワーが設置されており、その中の一つ、浜町地区の日本最大級の高さの津波避難タワーにタモリさんは登りました。車椅子利用者も避難しやすいようにスロープが設けられており、7階には降下シューターも完備されています。こうした設備は、町の人々の防災意識を高める一助となっているようです。
黒潮町では、津波被害を想定した新たな防災産業も生まれています。もともと雇用の場が少なく、人口流出が問題だったこの町では、南海トラフ地震のリスクが報じられたことでさらに人口が減少しました。それを食い止めるために誕生したのが、非常食用の缶詰製作所です。タモリさんは製作所を訪れ、缶詰の充填作業を体験しながら、この町ならではの防災への取り組みについて学びました。
室戸市の津波避難シェルターと地震予測のヒント
続いてタモリさんは、室戸市にある日本で唯一の津波避難シェルターを訪問しました。このシェルターは、住民が迅速に避難できるように設計されています。また、室戸岬では、30年以内に発生する確率約80%というデータを裏付ける重要なヒントがあるとされており、タモリさんはその根拠に驚かされました。
番組ではさらに、南海トラフ地震がもたらすパニックを多角的に分析しました。関西圏のマンションに暮らす3人家族を主人公にした“想定ドラマ”を通じて、地震発生直後の困難を描き、専門家の解説を交えながら、今後の対策について学びました。
都市を襲う津波「縮流」への警鐘
南海トラフ地震のもう一つの大きな懸念は、都市を襲う津波「縮流」です。震源域が陸地に近いため、津波の到達時間が最短で2分と非常に短い場所もあります。横浜や名古屋、さらには大阪などの都市も津波の危険に晒されており、首都圏での対策が急務とされています。
スタジオでは、地震研究の第一人者である東京大学名誉教授の平田直さん、備え・防災アドバイザーの高荷智也さん、津波研究の第一人者で中央大学教授の有川太郎さんが出演し、専門的な見解を述べました。彼らは「正しく知り、正しく恐れ、正しく備える」ことの重要性を強調し、視聴者に防災意識を高める必要性を訴えました。
南海トラフ地震は日本にとって非常に深刻な脅威ですが、これまでの取り組みや新たな防災産業の発展が、地域社会のレジリエンスを高める一助となることが期待されています。タモリさんの現地調査を通じて、視聴者は改めて防災の重要性を感じたことでしょう。
[山本 菜々子]